1992年私立大学入試偏差値・競争率一覧(文系編)
はる坊です。
今回は、私大バブル末期の1992年私立大学入試偏差値・競争率一覧(文系編)をお届けします。
Fランク大学?
BF(ボーダーフリー)?
大学全入時代?
そんな言葉も存在もカケラもなかった仁義なき大学入試時代です。
各校の偏差値は河合塾・駿台予備学校・代々木ゼミナール・進研のデータです。
偏差値の下に記載した倍率は、前年の1991年度入試のものです。
このデータに該当する入試に挑まれたのは、現役生だと1973年(昭和48年)~1974年(昭和49年)生まれの方ですね。
現在は、47歳~48歳とまさに社会の最前線で活躍されている世代です。
また、卒業時期が〝就職氷河期〟と合わさっているため、「大学入試で苦労。就職活動で苦労」された記憶をお持ちの方も結構おられるのではないでしょうか?
余談ですが、管理人も〝就職氷河期〟世代です。
新卒での就職機会は生涯でただ一度ですから、過去に経験がなく自分自身で過去との比較評価ができず、
周囲が「厳しい、厳しい」と連呼しており、不安でいっぱいではありましたが、
講義に興味を持ったことから親交が生まれた他学部の教授と大学の就職課(キャリアセンター)のサポートが手厚かったことで、無事内定をいただき、「ああ、新卒の就職活動ってこんな感じなんだ」と思って過ごした記憶があります。
もし、2021年卒・2022年卒でこのページをご覧いただいている方は、少しでも就職に関する情報とサポートを受けられて、他の方よりずっと有利に就職活動を進められることをオススメします。
謙遜して、
「また、エントリーシート(ES)落ちた」
とか
「全然、内定取れない」
周囲に言っておきながら、着実に就職活動を進めて、しれっと第1志望から内定を獲得している人がザラにいるので、就職活動に遠慮や同情は禁物です。
残念な話ですが、まだ日本では新卒一括採用が主流で、新卒しか採用しない大企業もありほどで、新卒での就活で失敗してしまうとリカバリーはかなり難しいです。
だからこそ、内定に向かって使える手はすべて使いましょう。
⇒参加者内定率96%のMeetsCompany

さて、それでは1992年度入試の難易度と前年度倍率に話を戻します。
私立大学法学部・経済学部・経営学部・商学部・国際関係学部・外国語学部の文系編をご覧ください。
法学部系統
札幌大学法学部
河合塾:47.5
駿 台:39.5
代ゼミ:50
進 研:50
倍 率:3.4倍
北海学園大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:4.7倍
東北学院大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:49.0
代ゼミ:54
進 研:54
倍 率:3.4倍
駿河台大学法学部
河合塾:47.5
駿 台:51.5
代ゼミ:53
進 研:56
倍 率:3.3倍
聖学院大学政治経済学部
河合塾:47.5
駿 台:41.5
代ゼミ:49
進 研:44
倍 率:19.1倍
獨協大学法学部
河合塾:60.0
駿 台:54.0
代ゼミ:59
進 研:64
倍 率:3.3倍
八千代国際大学(現・秀明大学)政治経済学部
河合塾:47.5
駿 台:41.5
代ゼミ:48
進 研:47
倍 率:9.5倍
青山学院大学法学部
河合塾:62.5
駿 台:57.0
代ゼミ:63
進 研:70
倍 率:6.9倍
亜細亜大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:48.5
代ゼミ:57
進 研:58
倍 率:7.2倍
学習院大学法学部
河合塾:62.5
駿 台:59.5
代ゼミ:64
進 研:70
倍 率:7.9倍
駒澤大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:54.0
代ゼミ:59
進 研:64
倍 率:5.1倍
慶應義塾大学法学部A方式
河合塾:70.0
駿 台:64.0
代ゼミ:69
進 研:75
倍 率:3.5倍
慶應義塾大学総合政策学部
河合塾:70.0
駿 台:60.0
代ゼミ:69
進 研:75
倍 率:10.4倍
國學院大学法学部A方式
河合塾:57.5
駿 台:53.5
代ゼミ:58
進 研:60
倍 率:6.7倍
国士舘大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:44.0
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:6.9倍
上智大学法学部
河合塾:70.0
駿 台:64.0
代ゼミ:67
進 研:79
倍 率:10.2倍
成城大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:56.5
代ゼミ:62
進 研:67
倍 率:2.9倍
成蹊大学法学部
河合塾:60.0
駿 台:54.5
代ゼミ:61
進 研:65
倍 率:7.9倍
専修大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:51.0
代ゼミ:59
進 研:63
倍 率:6.1倍
創価大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:49.5
代ゼミ:56
進 研:58
倍 率:5.4倍
大東文化大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:48.5
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:4.7倍
中央大学法学部
河合塾:65.0
駿 台:60.5
代ゼミ:66
進 研:74
倍 率:5.9倍
帝京大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:44.5
代ゼミ:50
進 研:50
倍 率:4.6倍
東海大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:49.0
代ゼミ:59
進 研:58
倍 率:9.4倍
東洋大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:51.5
代ゼミ:57
進 研:57
倍 率:9.8倍
日本大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:56.0
代ゼミ:60
進 研:63
倍 率:4.9倍
法政大学法学部
河合塾:60.0
駿 台:57.5
代ゼミ:61
進 研:67
倍 率:7.1倍
明治学院大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:53.5
代ゼミ:60
進 研:63
倍 率:6.7倍
明治大学法学部
河合塾:62.5
駿 台:59.5
代ゼミ:64
進 研:72
倍 率:5.4倍
明治大学政治経済学部政治学科
河合塾:65.0
駿 台:60.5
代ゼミ:64
進 研:71
倍 率:5.3倍
立教大学法学部
河合塾:65.0
駿 台:59.5
代ゼミ:64
進 研:70
倍 率:7.4倍
立正大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:49.0
代ゼミ:55
進 研:53
倍 率:8.9倍
早稲田大学政治経済学部政治学科
河合塾:70.0
駿 台:64.0
代ゼミ:69
進 研:81
倍 率:12.1倍
早稲田大学法学部
河合塾:67.5
駿 台:62.0
代ゼミ:67
進 研:79
倍 率:9.6倍
神奈川大学法学部A方式
河合塾:57.5
駿 台:52.0
代ゼミ:59
進 研:62
倍 率:4.6倍
山梨学院大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:44.0
代ゼミ:49
進 研:48
倍 率:7.4倍
愛知学院大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:55
進 研:57
倍 率:5.4倍
愛知大学法学部A方式
河合塾:57.5
駿 台:51.0
代ゼミ:58
進 研:63
倍 率:5.9倍
中京大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:44.0
代ゼミ:53
進 研:56
倍 率:6.8倍
南山大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:56.0
代ゼミ:62
進 研:69
倍 率:4.3倍
名城大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:49.0
代ゼミ:56
進 研:60
倍 率:4.8倍
同志社大学法学部
河合塾:67.5
駿 台:60.5
代ゼミ:66
進 研:77
倍 率:5.3倍
京都学園大学法学部
河合塾:47.5
駿 台:41.0
代ゼミ:49
進 研:49
倍 率:12.0倍
京都産業大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:51.0
代ゼミ:59
進 研:62
倍 率:3.9倍
立命館大学法学部A方式
河合塾:62.5
駿 台:59.5
代ゼミ:63
進 研:71
倍 率:6.3倍
龍谷大学法学部
河合塾:60.0
駿 台:49.0
代ゼミ:57
進 研:60
倍 率:9.5倍
関西大学法学部
河合塾:60.0
駿 台:54.0
代ゼミ:61
進 研:68
倍 率:5.6倍
近畿大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:5.6倍
摂南大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:44.0
代ゼミ:54
進 研:53
倍 率:5.2倍
大阪学院大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:42.0
代ゼミ:52
進 研:50
倍 率:9.7倍
関西学院大学法学部
河合塾:62.5
駿 台:58.0
代ゼミ:64
進 研:70
倍 率:3.6倍
甲南大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:49.5
代ゼミ:59
進 研:60
倍 率:4.9倍
神戸学院大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:5.0倍
姫路獨協大学法学部
河合塾:47.5
駿 台:42.5
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:4.2倍
奈良産業大学(現:奈良学園大学)法学部
河合塾:47.5
駿 台:39.5
代ゼミ:49
進 研:46
倍 率:7.6倍
広島修道大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:42.5
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:3.0倍
松山大学法学部
河合塾:52.5
駿 台:42.0
代ゼミ:56
進 研:58
倍 率:3.2倍
久留米大学法学部
河合塾:50.0
駿 台:39.5
代ゼミ:53
進 研:54
倍 率:4.1倍
西南学院大学法学部
河合塾:57.5
駿 台:53.0
代ゼミ:60
進 研:65
倍 率:5.4倍
福岡大学法学部
河合塾:55.0
駿 台:45.0
代ゼミ:56
進 研:59
倍 率:6.2倍
宮崎産業経営大学法学部
河合塾:45.0
駿 台:40.5
代ゼミ:51
進 研:52
倍 率:4.4倍
経済学部・経営学部・商学部系統
北海学園大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:44.5
代ゼミ:54
進 研:53
倍 率:4.2倍
北星学園大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:5.3倍
東北学院大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:42.0
代ゼミ:52
進 研:52
倍 率:5.3倍
白鴎大学経済学部
河合塾:47.5
駿 台:41.0
代ゼミ:55
進 研:55
倍 率:4.5倍
駿河台大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:49.5
代ゼミ:52
進 研:52
倍 率:5.4倍
城西大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:44.5
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:4.4倍
東京国際大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:44.0
代ゼミ:55
進 研:54
倍 率:6.8倍
文教大学情報学部
河合塾:50.0
駿 台:45.5
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:7.2倍
獨協大学経済学部A方式
河合塾:55.0
駿 台:52.5
代ゼミ:59
進 研:60
倍 率:5.4倍
千葉商科大学商経学部
河合塾:50.0
駿 台:44.0
代ゼミ:53
進 研:51
倍 率:6.3倍
東京情報大学経営情報学部
河合塾:47.5
駿 台:41.5
代ゼミ:50
進 研:46
倍 率:10.2倍
明海大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:13.5倍
青山学院大学経営学部
河合塾:62.5
駿 台:55.0
代ゼミ:62
進 研:67
倍 率:9.1倍
青山学院大学経済学部
河合塾:62.5
駿 台:56.0
代ゼミ:62
進 研:69
倍 率:8.9倍
亜細亜大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:51.0
代ゼミ:56
進 研:56
倍 率:12.2倍
学習院大学経済学部
河合塾:62.5
駿 台:58.0
代ゼミ:63
進 研:68
倍 率:7.1倍
駒澤大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:51.5
代ゼミ:59
進 研:62
倍 率:9.5倍
駒澤大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:49.5
代ゼミ:57
進 研:58
倍 率:10.8倍
慶應義塾大学経済学部A方式
河合塾:70.0
駿 台:64.0
代ゼミ:67
進 研:76
倍 率:4.9倍
慶應義塾大学環境情報学部
河合塾:70.0
駿 台:58.0
代ゼミ:67
進 研:74
倍 率:11.9倍
慶應義塾大学商学部A方式
河合塾:62.5
駿 台:61.5
代ゼミ:66
進 研:74
倍 率:3.4倍
國學院大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:52.0
代ゼミ:57
進 研:58
倍 率:8.9倍
国士舘大学政経学部
河合塾:52.5
駿 台:47.5
代ゼミ:52
進 研:50
倍 率:14.0倍
桜美林大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:53
進 研:53
倍 率:15.5倍
上智大学経済学部
河合塾:65.0
駿 台:61.0
代ゼミ:66
進 研:72
倍 率:9.3倍
成城大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:55.5
代ゼミ:60
進 研:63
倍 率:4.9倍
成蹊大学経済学部
河合塾:60.0
駿 台:56.5
代ゼミ:62
進 研:67
倍 率:7.5倍
専修大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:50.5
代ゼミ:58
進 研:59
倍 率:8.5倍
専修大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:51.5
代ゼミ:57
進 研:59
倍 率:10.8倍
創価大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:46.0
代ゼミ:54
進 研:55
倍 率:6.5倍
高千穂商科大学(現:高千穂大学)商学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:50
倍 率:8.6倍
大東文化大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:48.5
代ゼミ:56
進 研:55
倍 率:6.5倍
拓殖大学政経学部経済学科
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:14.5倍
中央大学経済学部
河合塾:62.5
駿 台:56.5
代ゼミ:62
進 研:67
倍 率:11.8倍
中央大学商学部
河合塾:62.5
駿 台:56.0
代ゼミ:62
進 研:65
倍 率:10.4倍
東海大学政治経済学部経済学科
河合塾:57.5
駿 台:51.0
代ゼミ:57
進 研:57
倍 率:10.6倍
東京経済大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:50.0
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:6.4倍
東洋大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:10.0倍
東洋大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:49.5
代ゼミ:57
進 研:58
倍 率:14.8倍
日本大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:52.5
代ゼミ:58
進 研:59
倍 率:8.1倍
日本大学商学部
河合塾:60.0
駿 台:52.0
代ゼミ:57
進 研:57
倍 率:10.6倍
武蔵大学経済学部A方式
河合塾:57.5
駿 台:54.0
代ゼミ:59
進 研:59
倍 率:7.0倍
法政大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:55.5
代ゼミ:61
進 研:64
倍 率:7.1倍
法政大学経済学部
河合塾:60.0
駿 台:55.0
代ゼミ:61
進 研:64
倍 率:7.1倍
明治学院大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:53.5
代ゼミ:61
進 研:63
倍 率:6.2倍
明治大学政治経済学部経済学科
河合塾:62.5
駿 台:58.0
代ゼミ:63
進 研:68
倍 率:6.2倍
明治大学商学部
河合塾:62.5
駿 台:57.0
代ゼミ:64
進 研:71
倍 率:8.6倍
明治大学経営学部
河合塾:65.0
駿 台:54.0
代ゼミ:62
進 研:68
倍 率:13.9倍
立教大学経済学部
河合塾:60.0
駿 台:59.5
代ゼミ:63
進 研:67
倍 率:5.6倍
立正大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:48.0
代ゼミ:54
進 研:50
倍 率:7.0倍
早稲田大学政治経済学部経済学科
河合塾:70.0
駿 台:62.0
代ゼミ:67
進 研:78
倍 率:11.2倍
早稲田大学商学部
河合塾:67.5
駿 台:59.5
代ゼミ:66
進 研:76
倍 率:12.7倍
和光大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:45.5
代ゼミ:49
進 研:48
倍 率:21.7倍
関東学院大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:48
代ゼミ:54
進 研:53
倍 率:12.0倍
産能大学(現:産業能率大学)経営情報学部
河合塾:52.5
駿 台:46.0
代ゼミ:53
進 研:54
倍 率:13.9倍
神奈川大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:52.0
代ゼミ:58
進 研:59
倍 率:8.1倍
神奈川大学経営学部
河合塾:55.0
駿 台:52.0
代ゼミ:57
進 研:59
倍 率:5.5倍
新潟産業大学経済学部
河合塾:47.5
駿 台:40.0
代ゼミ:50
進 研:47
倍 率:7.2倍
金沢経済大学(現:金沢星稜大学)経済学部
河合塾:50.0
駿 台:44.5
代ゼミ:48
進 研:46
倍 率:8.5倍
山梨学院大学商学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:49
進 研:47
倍 率:12.7倍
岐阜経済大学(現:岐阜協立大学)経済学部
河合塾:47.5
駿 台:40.5
代ゼミ:49
進 研:48
倍 率:4.0倍
愛知学院大学経営学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:54
進 研:55
倍 率:4.2倍
愛知学院大学商学部
河合塾:52.5
駿 台:43.5
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:5.5倍
愛知大学経済学部A方式
河合塾:55.0
駿 台:51.0
代ゼミ:57
進 研:60
倍 率:4.4倍
愛知大学経営学部A方式
河合塾:55.0
駿 台:51.5
代ゼミ:57
進 研:60
倍 率:4.4倍
中京大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:42.5
代ゼミ:53
進 研:53
倍 率:4.0倍
南山大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:57.5
代ゼミ:61
進 研:69
倍 率:4.5倍
南山大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:53.0
代ゼミ:61
進 研:64
倍 率:5.0倍
日本福祉大学経済学部A方式
河合塾:52.5
駿 台:46.0
代ゼミ:54
進 研:54
倍 率:7.3倍
名古屋学院大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:52
倍 率:5.3倍
名古屋経済大学経済学部
河合塾:47.5
駿 台:41.0
代ゼミ:50
進 研:50
倍 率:6.1倍
名古屋商科大学商学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:52
倍 率:13.0倍
名城大学商学部
河合塾:52.5
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:57
倍 率:4.1倍
京都産業大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:49.0
代ゼミ:57
進 研:59
倍 率:6.4倍
京都産業大学経営学部
河合塾:55.0
駿 台:48.0
代ゼミ:57
進 研:57
倍 率:7.3倍
同志社大学経済学部
河合塾:65.0
駿 台:59.0
代ゼミ:65
進 研:74
倍 率:8.0倍
同志社大学商学部
河合塾:65.0
駿 台:57.0
代ゼミ:64
進 研:72
倍 率:6.6倍
立命館大学産業社会学部A方式
河合塾:60.0
駿 台:56.0
代ゼミ:61
進 研:68
倍 率:8.5倍
立命館大学経済学部A方式
河合塾:60.0
駿 台:56.0
代ゼミ:62
進 研:68
倍 率:7.8倍
立命館大学経営学部A方式
河合塾:60.0
駿 台:56.5
代ゼミ:61
進 研:67
倍 率:8.8倍
龍谷大学経済学部
河合塾:60.0
駿 台:49.0
代ゼミ:57
進 研:59
倍 率:10.6倍
龍谷大学経営学部
河合塾:60.0
駿 台:49.0
代ゼミ:56
進 研:58
倍 率:12.7倍
関西大学経済学部
河合塾:60.0
駿 台:54.0
代ゼミ:60
進 研:64
倍 率:6.1倍
関西大学商学部
河合塾:60.0
駿 台:53.0
代ゼミ:60
進 研:63
倍 率:9.7倍
近畿大学商経学部
河合塾:57.5
駿 台:48.0
代ゼミ:56
進 研:56
倍 率:9.9倍
摂南大学経営情報学部
河合塾:50.0
駿 台:42.0
代ゼミ:55
進 研:51
倍 率:11.0倍
大阪学院大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:50
進 研:48
倍 率:7.2倍
大阪経済大学経営学部
河合塾:50.0
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:55
倍 率:7.4倍
大阪経済大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:48.5
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:4.9倍
大阪国際大学経営情報学部
河合塾:47.5
駿 台:42.5
代ゼミ:51
進 研:50
倍 率:9.1倍
大阪産業大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:50
進 研:49
倍 率:8.2倍
大阪商業大学商経学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:50
倍 率:6.8倍
追手門学院大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:41.5
代ゼミ:52
進 研:51
倍 率:6.6倍
阪南大学商学部
河合塾:47.5
駿 台:40.0
代ゼミ:51
進 研:48
倍 率:7.9倍
阪南大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:40.5
代ゼミ:52
進 研:48
倍 率:7.5倍
桃山学院大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:46.0
代ゼミ:54
進 研:54
倍 率:5.4倍
関西学院大学経済学部
河合塾:62.5
駿 台:58.5
代ゼミ:64
進 研:72
倍 率:7.7倍
関西学院大学商学部
河合塾:60.0
駿 台:56.5
代ゼミ:63
進 研:70
倍 率:7.9倍
甲南大学経営学部
河合塾:57.5
駿 台:52.0
代ゼミ:59
進 研:62
倍 率:8.3倍
甲南大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:52.5
代ゼミ:58
進 研:59
倍 率:5.9倍
神戸学院大学経済学部
河合塾:52.5
駿 台:47.0
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:6.1倍
姫路獨協大学経済情報学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:53
進 研:53
倍 率:5.7倍
流通科学大学商学部
河合塾:55.0
駿 台:42.0
代ゼミ:60
進 研:60
倍 率:6.9倍
帝塚山大学経済学部
河合塾:47.5
駿 台:40.5
代ゼミ:53
進 研:52
倍 率:4.8倍
広島修道大学商学部
河合塾:50.0
駿 台:43.0
代ゼミ:55
進 研:55
倍 率:4.7倍
松山大学経済学部
河合塾:50.0
駿 台:40.5
代ゼミ:55
進 研:57
倍 率:3.2倍
久留米大学商学部
河合塾:47.5
駿 台:40.5
代ゼミ:52
進 研:52
倍 率:4.2倍
九州産業大学商学部
河合塾:50.0
駿 台:40.0
代ゼミ:50
進 研:51
倍 率:5.4倍
九州産業大学経営学部
河合塾:47.5
駿 台:39.5
代ゼミ:49
進 研:50
倍 率:6.3倍
西南学院大学経済学部
河合塾:57.5
駿 台:52.5
代ゼミ:60
進 研:64
倍 率:5.6倍
西南学院大学商学部
河合塾:57.5
駿 台:51.5
代ゼミ:59
進 研:62
倍 率:6.7倍
福岡大学経済学部
河合塾:55.0
駿 台:45.5
代ゼミ:56
進 研:58
倍 率:6.5倍
福岡大学商学部
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:55
進 研:58
倍 率:7.2倍
熊本商科大学(現:熊本学園大学)経済学部
河合塾:52.5
駿 台:42.0
代ゼミ:53
進 研:54
倍 率:3.5倍
国際・国際関係学部系統
東京国際大学教養学部国際学科
河合塾:52.5
駿 台:44.5
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:4.8倍
文教大学国際学部
河合塾:50.0
駿 台:40.0
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:9.4倍
青山学院大学国際政治経済学部
河合塾:67.5
駿 台:61.5
代ゼミ:64
進 研:72
倍 率:10.2倍
亜細亜大学国際関係学部
河合塾:57.5
駿 台:49.0
代ゼミ:59
進 研:61
倍 率:12.3倍
共立女子大学国際文化学部
河合塾:55.0
駿 台:44.0
代ゼミ:57
進 研:60
倍 率:6.8倍
大東文化大学国際関係学部
河合塾:55.0
駿 台:49.0
代ゼミ:55
進 研:56
倍 率:6.8倍
津田塾大学学芸学部国際関係学科
河合塾:62.5
駿 台:60.0
代ゼミ:65
進 研:74
倍 率:3.0倍
日本大学国際関係学部
河合塾:55.0
駿 台:51.5
代ゼミ:58
進 研:60
倍 率:7.0倍
明治学院大学国際学部
河合塾:60.0
駿 台:53.5
代ゼミ:62
進 研:68
倍 率:6.9倍
中部大学国際関係学部
河合塾:50.0
駿 台:44.0
代ゼミ:54
進 研:56
倍 率:3.6倍
立命館大学国際関係学部A方式
河合塾:65.0
駿 台:56.5
代ゼミ:64
進 研:71
倍 率:9.6倍
大阪学院大学国際学部
河合塾:52.5
駿 台:39.5
代ゼミ:55
進 研:54
倍 率:8.6倍
九州国際大学国際商学部
河合塾:45.0
駿 台:39.0
代ゼミ:49
進 研:47
倍 率:7.2倍
外国部学部系統
札幌大学外国語学部
河合塾:50.0
駿 台:41.0
代ゼミ:53
進 研:54
倍 率:4.0倍
獨協大学外国語学部
河合塾:60.0
駿 台:55.0
代ゼミ:63
進 研:69
倍 率:3.6倍
神田外語大学外国語学部
河合塾:57.5
駿 台:51.5
代ゼミ:59
進 研:65
倍 率:5.3倍
明海大学外国語学部
河合塾:57.5
駿 台:44.0
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:13.5倍
麗澤大学外国語学部
河合塾:60.0
駿 台:46.5
代ゼミ:58
進 研:65
倍 率:6.2倍
杏林大学外国語学部
河合塾:55.0
駿 台:42.0
代ゼミ:54
進 研:55
倍 率:5.0倍
上智大学外国語学部
河合塾:67.5
駿 台:61.5
代ゼミ:66
進 研:77
倍 率:6.9倍
大東文化大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:48.5
代ゼミ:55
進 研:57
倍 率:5.6倍
拓殖大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:44.5
代ゼミ:54
進 研:55
倍 率:6.9倍
神奈川大学外国語学部A方式
河合塾:60.0
駿 台:54.0
代ゼミ:60
進 研:67
倍 率:7.5倍
北陸大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:44.5
代ゼミ:54
進 研:56
倍 率:4.9倍
常葉学園大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:40.0
代ゼミ:56
進 研:57
倍 率:3.1倍
南山大学外国語学部
河合塾:60.0
駿 台:56.0
代ゼミ:63
進 研:72
倍 率:5.2倍
名古屋外国語大学外国語学部
河合塾:57.5
駿 台:48.5
代ゼミ:59
進 研:65
倍 率:4.6倍
名古屋学院大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:47.0
代ゼミ:56
進 研:59
倍 率:5.0倍
京都外国語大学外国語学部
河合塾:60.0
駿 台:52.5
代ゼミ:61
進 研:68
倍 率:4.3倍
京都産業大学外国語学部
河合塾:55.0
駿 台:49.0
代ゼミ:58
進 研:60
倍 率:4.4倍
関西外国語大学外国語学部
河合塾:60.0
駿 台:52.5
代ゼミ:61
進 研:69
倍 率:6.4倍
大阪学院大学外国語学部
河合塾:55.0
駿 台:46.5
代ゼミ:55
進 研:58
倍 率:6.6倍
姫路獨協大学外国語学部
河合塾:52.5
駿 台:45.0
代ゼミ:55
進 研:57
倍 率:5.7倍
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
よろしければ、下記もご覧くださいませ。
今後もデータを更新してまいりますので、よろしくお願いいたします。
はる坊拝
⇒【私大バブル期】1985年【昭和60年】度~1991年【平成3年】度入試で私大の偏差値はここまで上昇した!1980年代後半から急上昇した私大偏差値の推移はこちらから(新しいタブが開きます)
⇒【私大バブル最盛期】1990年【平成2年】度 全国私立大学偏差値ランキング一覧表はこちらから(新しいタブが開きます)
⇒こちら『はる坊の雑記』偏差値関連記事 整理ページです。はこちらから(新しいタブが開きます)




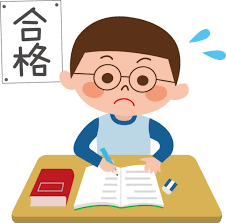

最近のコメント