王将フードサービスの常勤役員就任状況と新取締役に就任予定の池田勇気氏とは?
はる坊です。
今回は2023年6月28日の株主総会後に、
王将フードサービスの取締役 執行役員 営業企画部長に就任予定の池田勇気氏と
同社の常勤役員就任状況とについてまとめます。
池田勇気氏は、大阪経済大学卒業後に新卒入社した42歳
池田勇気氏は、1980年11月14日生まれの42歳です。
池田氏は高校時代から大阪経済大学経済学部経済学科卒業まで、餃子の王将 京橋駅前店でアルバイトをされていました。
そして、大学卒業後の2003年4月に新卒で入社。
京橋駅前店の現場スタッフを皮切りに、福島店・関目店・京橋駅前店・箕面半町店の店長を務め、
2009年11月に空港線豊中店の店長に着任。
この空港線豊中店は、火曜日~土曜日は24時間営業をしているお店です。
また、餃子の王将の店舗中、日本一の売上を誇る店舗でもあります。
この店舗の店長を任されるということは、将来の王将を背負って立つ人材として、
期待されているという意味を持ちます。
店長着任後、店舗の過去最高売上を更新した池田氏は、2014年にエリアマネージャーに昇格。
その後、2016年7月に営業企画推進部 副部長。
2017年8月 販売促進部 副部長
2018年6月 販売促進部長
とキャリアを重ね、
2022年には、執行役員 営業企画部長に就任。
今回の取締役就任に至ります。
王将フードサービスの常勤役員就任状況
繰り返しになりますが、新取締役候補の池田勇気氏は、1980年11月14日生まれの42歳です。
現在の王将フードサービスの常勤役員(社外役員を除く)を見てみると、
池田氏が若く期待されている人材であることがわかります。
代表取締役社長の渡邊直人氏が1955年8月19日大阪府生まれの67歳。
桃山学院大学経済学部卒業後の1979年に新卒入社。
大東隆行氏の後任として、2013年12月に社長に就任されています。
2021年度の役員報酬は1億1,200万円(金銭報酬:8,300万円 非金銭報酬:2,900万円)でした。
専務取締役 執行役員の門林弘氏が1963年1月17日大阪府生まれの60歳。
担当:営業本部長 西日本第1営業部長 営業サポート部長 王将大学学長 東京事務所長
大阪府立伯太高等学校卒業後の1981年に新卒入社されています。
専務取締役 執行役員の池田直子氏が1964年6月13日生まれの58歳。
担当:社長補佐 経営戦略本部長 経営デジタル推進準備室長
東京経済大学短期大学部商経科卒業後、新卒で安田火災海上保険株式会社(現在の損害保険ジャパン株式会社)入社。
その後、ご結婚・ご出産を経て、ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士として独立。
そして、2015年6月に王将フードサービス取締役に就任され、
常務取締役 取締役相談役 取締役社長補佐を経て、2022年6月より現職です。
なお、池田直子氏は、2023年6月28日の株主総会をもって、専務取締役を退任予定です。
常務取締役 執行役員の戸田光祐氏が1968年2月8日生まれの55歳。
担当:執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長
1996年4月に、株式会社三和総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社。
同社 チーフチーフコンサルタントを経て、2018年10月に王将フードサービス執行役員。
2019年6月より常務取締役を務めておられます。
なお、戸田光祐氏も、2023年6月28日の株主総会をもって、常務取締役を退任予定です。
常務取締役 執行役員の稲垣雅弘氏が1958年5月14日生まれの65歳。
担当:執行役員 管理本部長 経理部長 総務部長 広報IR部長
大学卒業後の1981年4月に、株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)へ入行。
同行 営業第七部長を経て、アビックス株式会社と株式会社アイディーズにて両社の管理部門担当役員を歴任。
2017年7月に王将フードサービスに入社と同時に経理部長に就任。
その後、執行役員→取締役→常務取締役と昇任され、同社の管理部門を統括する立場になられています。
もうひとりの新取締役候補 山田誠氏にも注目
前述した池田勇気氏とともに、もうひとり常勤取締役に就任予定の方がおられます。
現在、執行役員 管理本部 副本部長・経営戦略本部 副本部長・情報サービス部長を務められている、
山田誠氏です。
山田氏は1966年12月26日生まれの57歳。
京都産業大学経済学部経済学科卒業後の1989年4月に株式会社ダイエーに入社。
ローソンへの出向を経て、2000年5月に正式転籍。
その後、2002年10月にフューチャーアーキテクト株式会社に転職。
2010年3月には、佐川急便グループの社内ITを担当するSGシステム株式会社に転じて、同社のIT関連運用の管理職として活躍。
2012年9月には、親会社のSGホールディングスにて、グループ全体のITを担当。
2018年4月には、SGシステムに戻られ、管理部長として、総務・人事・法務・経理を統括。
2022年2月に、王将フードサービスに入社。
2022年7月には、情報サービス部長に就任。
2023年2月には、執行役員に就任されると同時に、管理本部 副本部長と経営戦略本部 副本部長を兼任されるに至ります。
2023年6月28日の株主総会をもって、専務取締役 経営戦略本部長 経営デジタル推進準備室長を退任される
池田直子氏の後継者として、
また、常務取締役 管理本部長の稲垣雅弘氏を支える立場となられるのではないでしょうか。
王将フードサービスの年収について
最後に、現在の王将フードサービスの給与・年収について触れます。
月額の給与ベースは飲食業界で高いほうになります。
過去には、残業代の不払い(サービス残業)が問題になっていたようですが、
現在は、残業代はキッチリ払われているようです。
年収は2年目の店舗スタッフで380万円以上。
副店長で500万円~600万円
店長で700万円~800万円
エリアマネージャーで800万円~900万円
王将フードサービスのボーナスについて
気になるボーナスですが、夏・冬・決算の年3回支給です。
ただし、ボーナス額はあまり期待ができないようです。
会社や店舗の業績や個人査定もありますが、
年間で1ヶ月~3ヶ月というところです。
月額給与を手厚くして、賞与は少なめ、という形のようです。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
よろしければ、下記もご覧くださいませ。
今後もデータを更新してまいりますので、よろしくお願いいたします。
はる坊拝
餃子の王将を展開する 王将フードサービス店頭公開(JASDAQ上場)時の情報
餃子の王将を展開する王将フードサービスは、1993年3月16日に株式店頭公開(現在のJASDAQ上場)を果たしました。
上場時のデータは以下のとおりです。
株式会社 王将フードサービス
会社設立:1974年7月
店頭公開:1993年3月
資 本 金:19億100万円
総 資 産:394億5600万円
株主資本:88億8300万円(22.5% 748円)
借 入 金:198億1000万円
金融収支:▲6億7300万円
従業員数:748名(平均年齢 31.6歳)
平均賃金:378,158円
株主構成:
加藤欣吾 287万1000株(24.1%)
加藤潔 265万1000株(22.3%)
加藤朝雄 179万5000株(15.1%)
加藤梅子 93万2000株(7.8%)
従業員持株会 30万1000株(2.5%)
加藤ひろみ 22万0000株(1.8%)
大東隆行 20万3000株(1.7%)
加藤貴司 20万3000株(1.7%)
加藤英里 20万3000株(1.7%)
加藤真人 20万3000株(1.7%)
役員構成:
代表取締役社長:加藤朝雄
取締役副社長 :望月邦彦
専務取締役 :加藤潔
常務取締役 :加藤欣吾
常務取締役 :大東隆行
常務取締役 :鈴木和久
取締役 :土肥原啓二
取締役 :宮嶋廣正
取締役 :宮光正
取締役 :知久平芳美
取締役 :森田八寿広
取締役 :村上武敏
常勤監査役 :小坂晴一郎
監査 :野中智弘
上場当時の王将は、日銭が入る商売とはいえ、あまり財務状況が良いとはいえず、公募株式で得た資金は、借入金返済に充てるつもりだったようです。
王将フードサービス 業績推移
それでは、1989年~1992年までの餃子の王将の決算を見ていきましょう。
急成長期には終わりを告げていますが、しっかり順調に伸びています。
1989年3月期決算:
(こちらのみ変則決算)
売上高:221億1,700万円
営業利益:24億2,100万円
経常利益:12億7,700万円
最終利益:5億1,900万円
1990年3月期決算:
売上高:265億3,200万円
営業利益:29億2,000万円
経常利益:13億8,300万円
最終利益:5億1,900万円(1989年3月期と同額)
1991年3月期決算
売上高:276億7,770万円
営業利益:32億6,000万円
経常利益:20億6,800万円
最終利益:9億2,000万円
1992年3月期決算
売上高:288億9,000万円
営業利益:35億6,900万円
経常利益:20億6,800万円
最終利益:12億5,100万円
餃子の王将を展開する王将フードサービスと大阪王将を展開する大阪王将(イートアンドホールディングス)との関係は?
日本に〝王将〟は2つあります。
王将フードサービスが運営する「餃子の王将」
イートアンドホールディングス傘下の事業会社・大阪王将が運営する「大阪王将」です。
大阪王将の創業者・文野新造氏は加藤朝雄氏の親族といわれています。
最初、京都に店舗展開を進めていた餃子の王将からのれん分けをしてもらう形で、1969年9月に大阪・京橋に中華料理店を開いたのが大阪王将の始まりです。
餃子の王将との違いは、まず経営スタイルです。
文野氏の中華料理店のメニューは、餃子とチャーハン、ラーメンの3品のみでしたが、餃子が一人前50円であったことから、安くてうまいものに目のない大阪人のハートを、いきなりガッチリと掴みます。
文野氏は店の売上が餃子中心であることに着目して、1969年3月から餃子専門店に業態を変更します。

餃子のみにメニューを絞ったことで、構えの大きい店舗展開が必要がなくなり、大阪王将は順調に店舗を増やしていきます。
そして、文野新造氏の個人事業から、1977年8月には、大阪王将食品株式会社に法人成りを果たします。
二代目社長となる文野直樹氏は、この頃から厨房に立って店の経営に携わっていました。
1982年には100店舗を達成しますが、一説によると、大阪王将の店舗を京都に出店したことにより、加藤朝雄氏との関係が悪化。商標権を巡って裁判沙汰にまでなってしまします。
結局、1985年に和解が成立しますが、1980年代前半に大阪証券取引所(新市場ベンチャー向け)2部への上場を目指していた加藤氏にとっては、この裁判が上場への大きなネックになったのかもしれません。
この当時、この大阪証券取引所2部に新しく作られた新市場で上場を果たして、のちに東証1部上場企業となった会社にコナミホールディングスがあります。
その後、餃子の王将と大阪王将は袂を分かち、お互いに独自の経営戦略で事業を発展させていきます。
大阪王将は、1990年代初めに商事部という部署を創設します。1993年9月には商事部から冷凍食品の餃子を生協向けに販売を開始。
自宅でも大阪王将の味が楽しめるようになりました。
その後、社名も大阪王将食品から大阪王将に変更。
そして、2002年1月にはイートアンド株式会社にまたも商号変更します。
堅実な店舗展開と冷凍食品の販売を進めながら、東京進出を果たし、2011年6月には大阪証券取引所JASDAQ市場に株式を上場。
2002年11月に東京証券取引所第2部上場を経て、2013年11月に東京証券取引所第1部に指定替えをおこないました。
晴れて、東証1部上場企業となった訳です。
餃子の王将を展開する王将フードサービスと大阪王将を展開する大阪王将(イートアンドホールディングス)歴代社長
ちなみに、『餃子の王将』を展開する王将フードサービスの創業者・社長が加藤朝雄氏で、
二代目社長がアサヒビールより招聘した望月邦彦氏。
三代目社長が加藤朝雄氏の長男・加藤潔氏。
四代目社長が大東隆行氏。
現在の五代目社長が渡邊直人氏です。
渡邊氏は、1955年8月19日生まれの67歳。1979年に桃山学院大学経済学部を卒業後、新卒入社。
1984年12月には早くも営業部次長となり、主に東京地区のエリアマネージャーや地区本部長を経て、
2004年に取締役、2008年に常務取締役となり、2013年12月に代表取締役社長に就任されています。
『大阪王将』を展開するイートアンドホールディングスの創業者が現在の代表取締役会長の文野直樹氏の父親である文野新造氏です。
創業メンバーである佐野文夫氏と本木健二氏とともに1969年9月に大阪・京橋に中華料理店を出店したところ、
餃子の売れ行きがダントツであったことから、早々に、餃子専門店に業態を変えています。
株式会社イートアンドホールディングスの代表取締役会長CEO 文野直樹氏の経歴
イートアンドホールディングス代表取締役会長CEOは文野直樹(ふみの なおき)氏です。
1959年11月29日生まれの62歳。
啓光学園高校を卒業後、大阪学院大学経営学部に進学するも1980年に中退。
実父・文野新造氏が経営する大阪王将食品に正式入社して、1984年7月に社長に就任したという経歴の持ち主です。
1996年8月に株式会社大阪王将に商号を変更。
2002年1月にイートアンド株式会社に商号を変更。
2011年6月に株式をJASDAQ市場に上場。
2012年11月に東京証券取引所第2部に上場。
2013年11月には、ついに東京証券取引所第1部上場を果たしています。
そして、2020年11月には、持株会社への移行とともに、株式会社イートアンドホールディングスとなり、大阪王将の運営会社は株式会社大阪王将となっています。
株式会社イートアンドホールディングスの取締役社長COO 仲田浩康氏の経歴
株式会社イートアンドホールディングスの取締役社長COOは仲田浩康(なかた ひろやす)氏です。
大阪王将の冷凍食品を扱う事業会社の株式会社イートアンドの代表取締役社長も兼任されています。
仲田氏は1964年4月26日生まれの57歳で、高校を卒業後、当時、流通業界で最大手だったダイエーに入社。
23歳で最年少主任となるなど活躍をしたのち、2000年8月に大阪王将に転職。
ご本人がインタビューで語られているところでは、ダイエーでは実績を残されていたので、大阪王将に移られた際には、給与・年収ともにダウンしたそうです。
その後、2001年7月に商事部部門長。2004年6月に取締役。2009年4月に取締役 常務執行役員 トレーディング本部長。
2012年4月 専務取締役。2017年6月にはついにイートアンドの代表取締役社長に就任。
持株会社移行後は、取締役社長COOに就任されています。
また、社会人となっても向学心を忘れず、関西学院大学大学院に進み修了されています。
よって、最終学歴は関西学院大学大学院修了となっています。
株式会社大阪王将の代表取締役社長 植月剛氏の経歴
大阪王将を運営する株式会社大阪王将の代表取締役社長は植月剛(うえつき たけし)氏です。
持株会社である株式会社イートアンドホールディングスの取締役も兼任されています。
植月氏は1972年7月13日生まれの49歳で、龍谷大学社会学部卒業後、1995年4月に大阪王将に新卒入社。
その後、2006年6月に取締役。2009年4月に取締役 執行役員 王将営業本部長。
大阪王将の海外事業部門も統括します。
2012年4月には、取締役 常務執行役員 王将営業本部長。
2019年4月に常務取締役 外食事業統括兼海外戦略本部長。
と順調にキャリアを積んで、2020年10月に大阪王将の代表取締役社長に就任されています。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
はる坊拝
こちらの記事もよく読んでいただいています。
よろしければ、お読み下さい。
⇒日本百貨通信販売・杉山グループ総帥 杉山治夫の生涯 その1(新しいタブが開きます)
⇒社員の最高平均年収2,183万円!資産約2兆8420億円 キーエンス創業者・滝崎武光氏はどこまでもミステリアス①(新しいタブが開きます)
⇒【ドラクエ王】スクウェア・エニックスの創業者 福嶋康博の人生がスゴすぎる①(新しいタブが開きます)
何かございましたらこちらまで。
ツイッター:はる坊の雑記Twitter
リンク
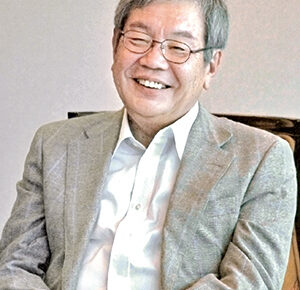




最近のコメント